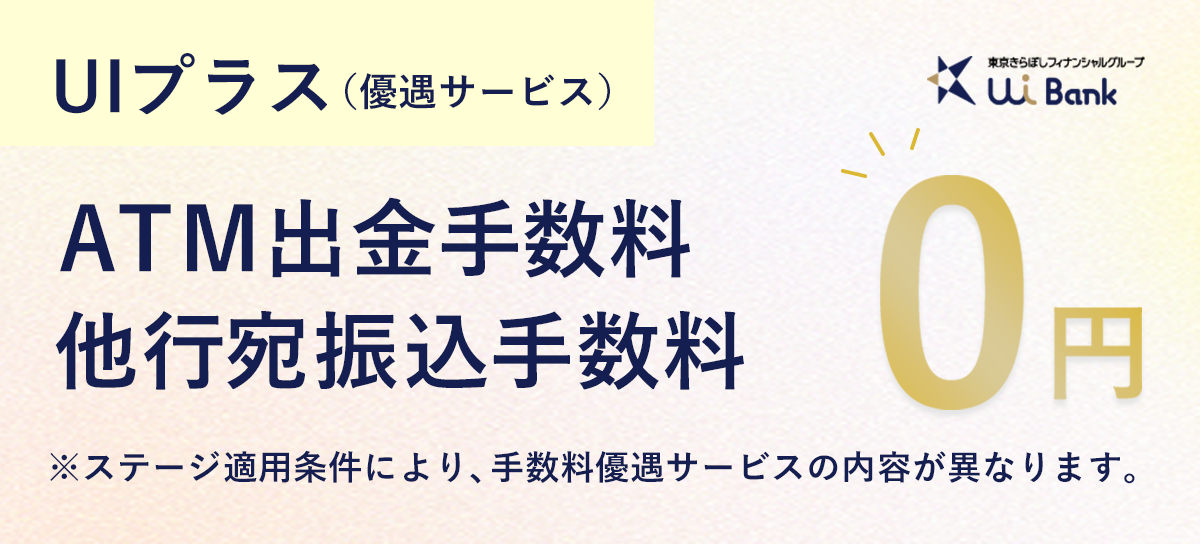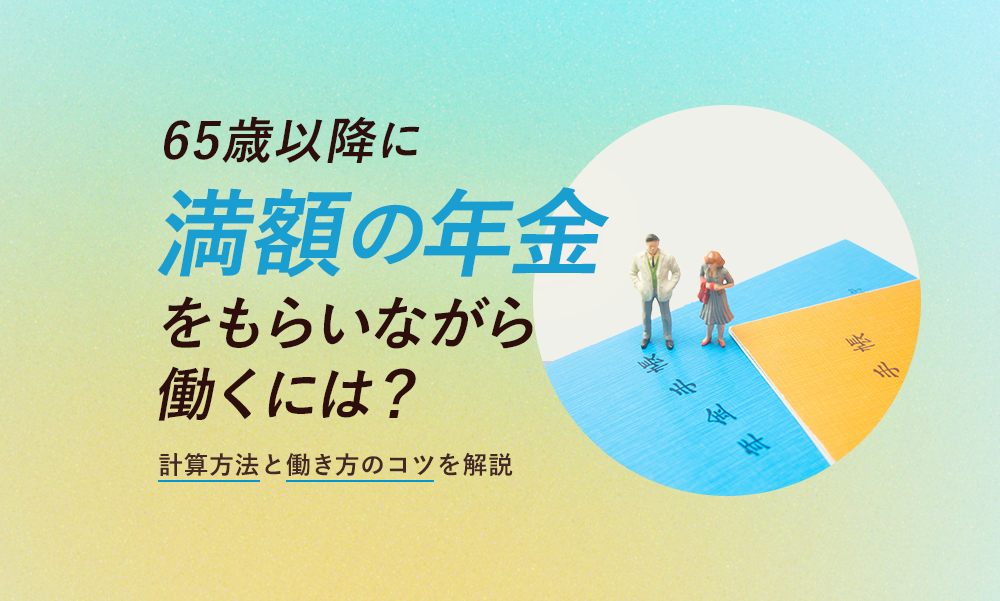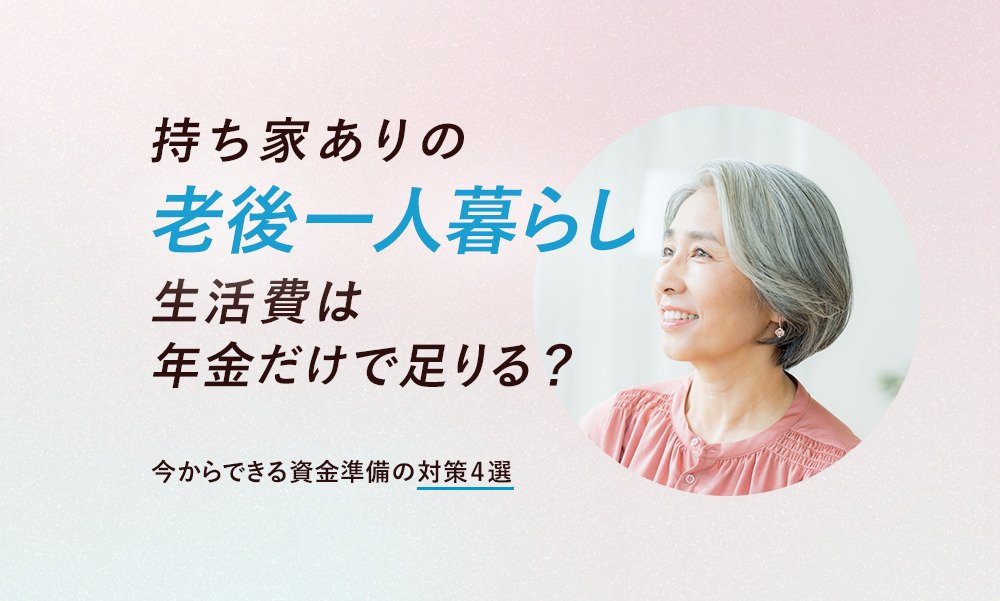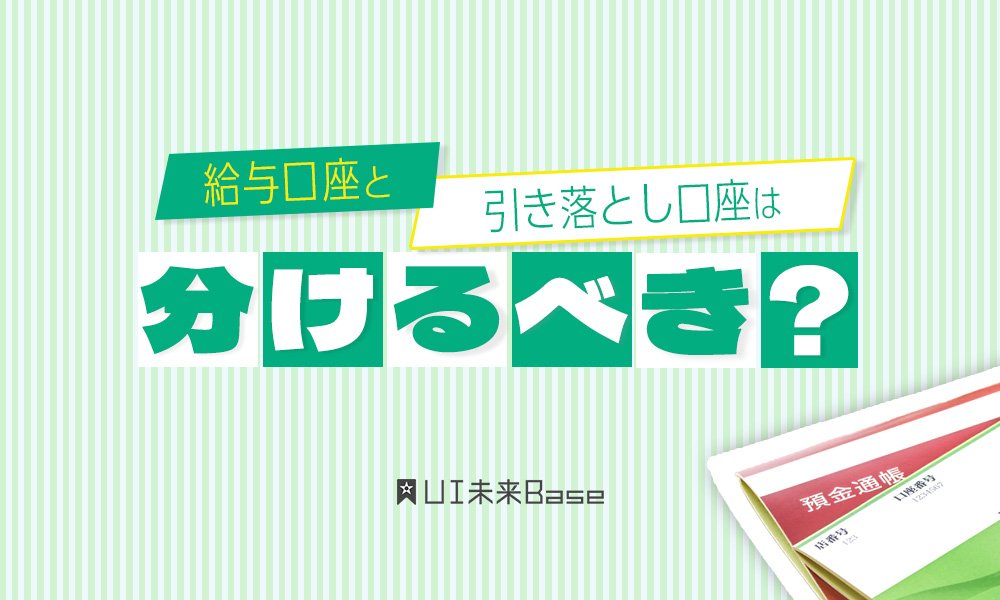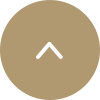夫婦の生活費折半はおかしい?納得できる負担割合の決め方を解説!
2025年08月22日
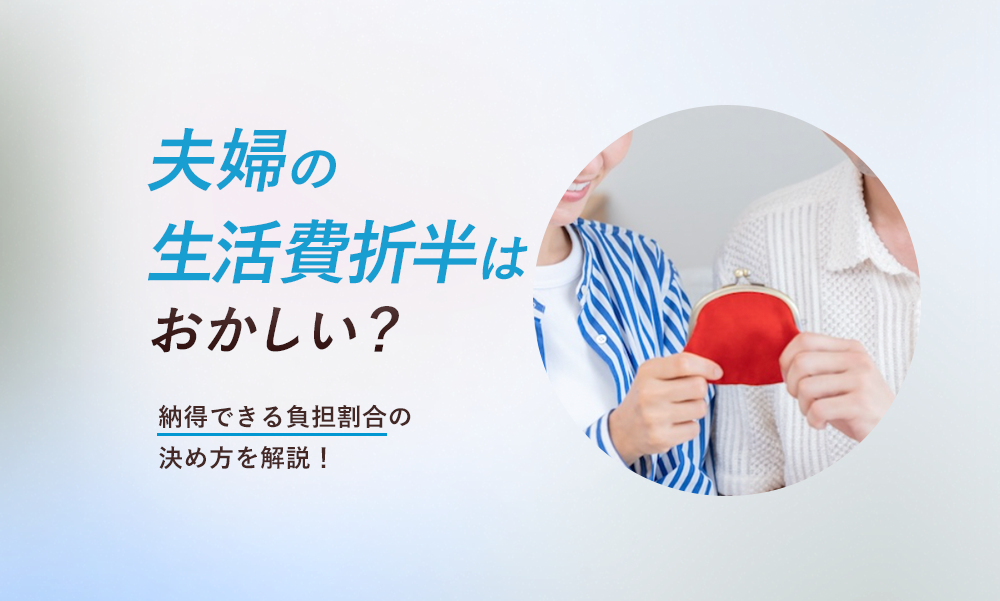
「夫婦の生活費を折半にしてるけど、本当にこれでいいの?」そんな疑問を感じていませんか?
本記事では、生活費を折半にしている夫婦の実際の割合や、「折半はおかしい」と感じやすい具体的な3つのケースを紹介。また、生活費を折半することによるメリット・デメリット、夫婦が納得できる生活費の負担割合までを詳しく解説します。
本記事を読めば、ご自身に合った家計管理のヒントがきっと見つかります。お金のモヤモヤを解消し、より良い夫婦関係を築くための参考にしてください。
家計管理でお悩みの方は、アプリでシンプルな操作が可能な「UI銀行」がおすすめです。お金の流れがアプリで明確になるため、夫婦で納得のいく家計づくりを始めるのに役立ちます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
\使いやすいアプリで家計管理!/
「UI銀行の詳細」をチェックする
- 【データで見る】生活費を「折半」している夫婦の割合は?
- ここが魅力!夫婦で生活費を折半する3つのメリット
- 要注意!夫婦の生活費折半で起こりがちな3つのデメリット
- 「おかしい」と感じたら見直したい!夫婦が円満になる生活費の負担割合の決め方
- 夫婦の生活費は納得できるルールづくりが大切!

結婚情報サービス「ゼクシィ」が実施した調査によると、共働き夫婦の生活費負担の割合は次のようになっています。
-
【共働き夫婦の生活費負担割合】ゼクシィ調べ
- ● 全額負担:16.4%
- ● 一部負担:46.4%
- ● 折半:37.3%
参考:ゼクシィ(2023年調査)「共働き夫婦の「生活費」の負担割合って?円満な分担ルールを解説」
この調査結果を見ると、「一部負担」つまり夫婦で負担割合を変えている家庭が46.4%と最も多く、次いで「折半」が37.3%という結果でした。つまり、生活費を完全に半分ずつにしている夫婦は全体の4割弱であり、必ずしも「折半が当たり前」とは限らないことがわかります。
また「一部負担」の夫婦は、それぞれの収入に応じて負担額を決めているケースが多いようです。例えば、収入が7対3の割合なら生活費もそれに合わせて分担するといった形です。「全額負担」を選んだ家庭では生活費を負担しないほうが貯蓄を専門に担当するなど、役割を分けているケースもあります。

生活費の折半には、不公平感を感じやすい側面がある一方で、見逃せないメリットも存在します。ここでは、夫婦で生活費を折半にすることで得られるおもな3つのメリットを紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
メリット1.家計管理がシンプルでわかりやすい
生活費を夫婦で折半にする最大のメリットは、家計管理がシンプルでわかりやすい点です。
毎月、夫婦それぞれが決まった金額を出し合うだけなので、複雑な計算は必要ありません。例えば、「毎月の生活費は20万円」と決めたのであれば、夫が10万円、妻が10万円を共通の財布に入れます。この明確なルールにより、日々の家計管理の負担が減ります。
特に夫婦の収入が同程度で、「お金の管理にあまり手間や時間をかけたくない」と考えている方にとっては、このわかりやすさが大きな魅力となるはずです。
メリット2.気兼ねなく趣味や交際費に使える
毎月決まった額を生活費として拠出すれば、残りの収入は基本的に各自が気兼ねなく使えるお金です。「今月は趣味の道具を買いたい」「友達と旅行に行きたい」といった個人的な支出に対して、相手の顔色をうかがったり、都度許可を得たりする必要がなくなるため、気持ちに余裕が生まれます。
この「金銭的な自由度」は夫婦間の不要な干渉を減らし、個人の満足度を高めることにもつながります。
もし、自身で自由に使えるお金を手軽に管理したいなら、「UI銀行」がおすすめです。例えば、女性の方限定で開設できる「女神のサイフ(普通預金)」なら、普通預金金利も魅力的で、アプリから美容やヘルス、フェムテック関連のクーポンもご利用可能です。
男女問わずライフスタイルに合った管理方法を見つけられるUI銀行のサービス詳細は、下記リンクをご覧ください。
\使いやすいアプリで家計管理!/
「UI銀行の詳細」をチェックする
メリット3.共通口座に一定額ずつ入れて貯蓄しやすい
生活費を折半にするというルールは、夫婦で協力して貯蓄を進めるうえでも役立ちます。
毎月の生活費とは別に、例えば「貯蓄用の共通口座」を設け、そこに毎月夫婦それぞれが決まった金額をコツコツと入金していくという方法です。夫婦それぞれが負担する貯蓄額が明確になり、マイホームの頭金や子供の教育資金など、共通の目標に向けて資産形成が進みます。
ただし、夫婦それぞれの収入にある程度の余裕があり、貯蓄の目標についてもきちんと話し合っておくことが大切です。ルールがシンプルだからこそ続けやすく、将来に向けた安心感を夫婦で共有できるのは大きな利点といえるでしょう。

生活費の折半は、一見すると公平でシンプルな方法に思えるかもしれません。しかし、思わぬ落とし穴が潜んでいることもあるのです。ここでは、夫婦の生活費を折半にすることで生じやすい3つのデメリットを紹介します。
これらの内容を事前に知っておくことで、対策を考えるきっかけになるはずです。
デメリット1.収入差があると不公平に感じやすい
生活費を折半にする際に最も不公平感が生じやすいのが、夫婦の間に収入差があるケースです。
例えば、夫の手取り額が45万円、妻の手取り額が20万円のケースで考えてみましょう。毎月の生活費が30万円かかる場合、夫婦できっちり15万円ずつの負担です。夫にとっては収入の3分の1ですが、妻にとっては収入の半分以上が生活費に消えてしまうことに。
このような経済的負担は心身のストレスにつながるだけでなく、場合によっては個人のキャリアプランや自己投資への意欲を削いでしまうおそれもあります。お互いの収入状況を考慮しない一律の折半は、かえって不公平感を生む原因になり得るといえるでしょう。
デメリット2.家事・育児の偏りが不満につながる
日本だけでなく多くの先進国で見られる傾向ですが、特に女性が仕事に加えて家事・育児という「見えない労働」あるいは「無償労働」の多くを担っているケースは少なくありません。
総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」では、「6歳未満の子供を持つ共働き世帯」の妻の1日の家事関連時間は平均6時間33分に対し、夫は1時間55分と大きな隔たりがありました。さらに、OECD(経済協力開発機構)の調査など国際比較データを見ても、多くの国で女性が男性の数倍もの時間を家事・育児に費やしている実態が示されています。
結果として、自分のための自由な時間や休息時間が極端に少なくなり、いわゆる「タイムプア(時間貧困)」と呼ばれる状態に陥ってしまうおそれもあります。一見平等に見える生活費の折半も、時間の使い方や心身の余裕に大きな不均衡があれば、夫婦関係の満足度も低下してしまうかもしれません。
デメリット3.急病・引越し・冠婚葬祭などの大きな出費で揉めやすい
予期せぬ大きな出費が発生した際に、夫婦間で揉めてしまう可能性があるのも生活費折半のデメリットのひとつです。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 突然の病気やケガで高額な医療費が必要になった
- 会社の都合で急な転勤が決まり、引越し費用が必要になった
- 親族の結婚式や葬儀でまとまったお金が必要になった
厳格に折半ルールを適用していると、「これは生活費ではないから各自で対応すべき」「これは二人に関わることだから折半すべき」といったように、どちらがどれだけ負担するのかで意見が対立しやすくなります。
このような突発的な大きな出費で困らないためにも、どのように対応するのか、共通の予備費を設けるのかといったルールを決めておく必要があるでしょう。

「生活費の折半、なんだか合ってないかも…」。もしそう感じ始めたなら、それは夫婦で家計管理を見直す良いチャンスです。ここでは、夫婦円満につながる生活費の負担割合の決め方を3パターン紹介します。
それぞれの特徴を理解し、自分たちに合った方法を探ってみましょう。
パターン1.収入に応じて負担割合を決める
夫婦の「不公平感」をなくす生活費の分担方法のひとつが、それぞれの収入の割合に応じて負担額を決めるというやり方です。
例えば、夫の手取り額が40万円、妻の手取り額が20万円であれば、収入の比率は2:1です。月の生活費が30万円かかる場合は、夫が20万円、妻が10万円を負担します。こうすることで、収入が少ない側も無理なく生活費を拠出でき、手元に残るお金にもある程度の余裕が生まれます。
実際に、結婚情報サービス「ゼクシィ」の調査でも、「収入差に応じて男性が多めに負担している」「前年の源泉徴収額を参考にして負担比率を決めている」といった声が寄せられています。
参考:ゼクシィ(2023年調査)「共働き夫婦の「生活費」の負担割合って?円満な分担ルールを解説」
この方法を取り入れるには、お互いの収入をオープンにする必要がありますが、より納得感のあるルールを作りやすい条件といえるでしょう。
パターン2.生活費の項目別に分担する
生活費の負担方法として、家賃や住宅ローンは夫、食費や日用品は妻、といったように費目ごとに支払う担当を決めるという方法もおすすめです。
例えば、
- 大きな固定費である家賃は収入の多い夫が担当
- 日々の変動費である食費や雑費は妻が担当
というように、いくつかの費目を組み合わせて分担します。
ただし、月々の費目ごとに支出額の変動があるため、トータルで見るとどちらかの負担額が大きくなってしまうおそれがあります。
定期的にお互いの負担状況を確認し、「今月は食費がかさんだから、来月は少し割合を変えよう」といったように、状況に応じて調整すると良いでしょう。
パターン3.それぞれの専用口座を作って管理する
夫婦の生活費管理では、お金の流れを「見える化」し、透明性を高めることが大切です。
例えば、夫婦それぞれがUI銀行の口座を開設し、毎月決めた生活費の分担額を生活決済用の口座(ローン、お子さんの給食費など)に入金します。UI銀行の口座間であれば資金の移動は無料なので、必要に応じて夫婦いずれか一方の口座に生活費を集約することも可能です。
さらに、UI銀行が提供するサービス「UIプラス」なら、総預金の1ヵ月平均残高に応じて他行への振込手数料およびATM出金手数料が月最大20回まで無料。生活費の振り分けにかかるコストを抑えられます。
※「女神のサイフ(普通預金)」をご利用のお客さまはUIプラスが適用されません。
それぞれのスタイルに合ったお金の管理をしたい方は、ぜひUI銀行をご検討ください。
\他行への振込手数料およびATM出金手数料が月最大20回まで無料!/
「UI銀行のUIプラス」をチェックする

夫婦の生活費、特に「折半」というルールに「おかしいかも…」と感じていた方も、この記事を通して少し視界が開けたのではないでしょうか。
生活費の分担に「これが正解」といえる方法はありません。大切なのは、夫婦がお互いの価値観や収入状況を理解し合い、納得できる自分たちらしいルールを作っていくことです。
この記事で紹介したメリット・デメリットや具体的な分担方法を参考にして、ご自身に合った家計管理のヒントにしてください。
\他行への振込手数料およびATM出金手数料が月最大20回まで無料!/
「UI銀行のUIプラス」をチェックする
・本記事は2025年8月22日の各種情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場や市場環境、制度の改正等を保証するものではありません。
企業プロフィール

株式会社UI銀行
UI銀行は、連携パートナーやきらぼし銀行を始めとしたきらぼしグループ各社と協働し、対面・非対面それぞれの良さを活かした多様なサービスを通じ、お客さまのお金だけでなく、健康や知識、人とのつながりといった見えない資産=「わたし資産」を増やすお手伝いをしていきます。

現在のあなたはどんなタイプ?9つのわたし資産の重要度をAIで判定!
あなた自身の多様な資産を知り、わたし資産をふやそう!
わたし資産スコアをためるとガチャ抽選で、プレゼントがもらえる企画を実施中!!