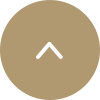住宅ローン控除を最大限に活用!押さえておくべき4つのポイントを徹底解説!
2025年06月24日
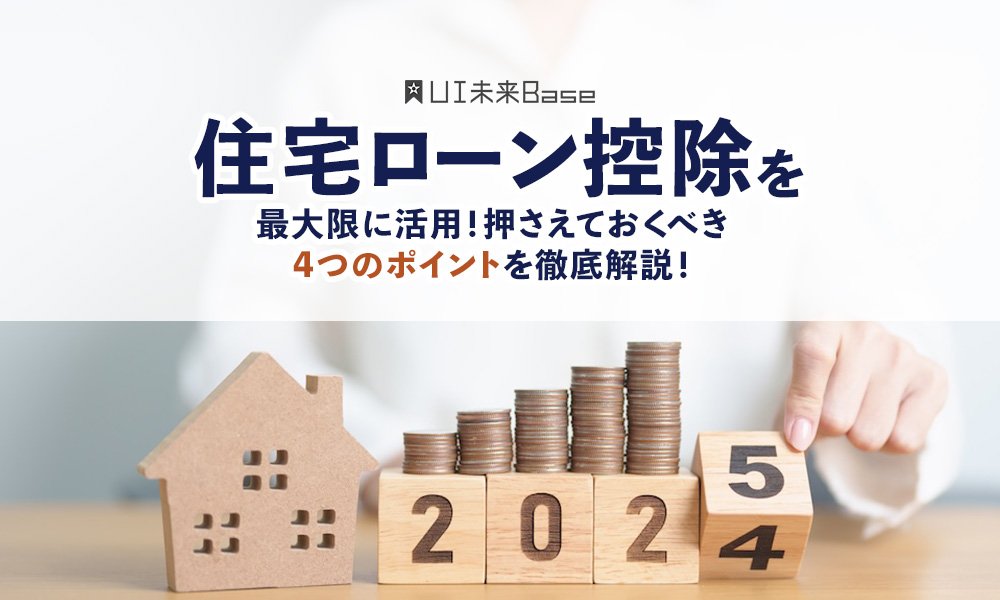
住宅ローン控除は、マイホーム取得において重要な制度のひとつです。特に、「新築住宅の借入限度額」「省エネ基準の扱い」「子育て世帯への優遇措置」などは、多くの方が関心を持つポイントでしょう。
本記事では、これらの疑問に答えるとともに、住宅ローン控除の仕組み、控除額の計算方法、申請手続きや必要書類について解説します。
住宅ローン控除を最大限に活用して、理想のマイホームを手に入れるための第一歩を踏み出しましょう!
>>>>「今すぐ住宅ローン控除の改正ポイントを知りたい方はこちら」<<<<
- 住宅ローン控除とは?制度の概要と目的を解説
- 押さえておくべき住宅ローン控除のポイントは4つ
- 住宅ローン控除はいくら戻る?計算方法を解説
- 住宅ローン控除の申請方法と必要書類
- 制度のポイントを理解して住宅ローン控除を最大限に活用しよう

住宅ローン控除(正しくは「住宅借入金等特別控除」)は、マイホームの購入やリフォームを検討している方にとってぜひ知っておきたい制度のひとつです。
-
【住宅ローン控除とは】
“無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。”
この制度を利用すると、住宅ローンの年末残高の一定割合(原則0.7%)を所得税から控除できます。さらに、所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税からも一部控除されるため、税金の負担を大きく軽減できるのです。
控除期間は、新築住宅や買取再販住宅の場合は原則13年間、中古住宅の場合は原則10年間です。この制度を利用するには、住宅の種類や床面積、年収などの条件を満たす必要があります。また、初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で手続きが必要です。
次章以降からは、制度のポイントや具体的な控除額の計算方法、申請方法について詳しく解説していきます。

住宅ローン控除は、社会状況の変化や政策に応じて見直されることがあります。そのため、住宅ローン控除を最大限に活用するには制度の情報を正しく理解しておかなければなりません。
特に押さえておくべきポイントは次の4つです。
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
ポイント1:新築住宅・買取再販の借入限度額
新築住宅および買取再販住宅に入居した場合の住宅ローン控除の借入限度額は次のとおりです。
| 住宅ローン控除の借入限度額 | ||
| 2023年以前に入居 | 2024年以降に入居 | |
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
具体的にどの程度縮小されるかは、住宅の種類や性能によって異なります。例えば、2024年以降に長期優良住宅や低炭素住宅などの省エネ性能が高い住宅に入居した場合は、住宅ローン控除の借入限度額は4,500万円です。
これから新築住宅の購入を検討している方は、住宅の種類や性能をよく確認し、住宅ローンの借入額や返済計画を慎重に検討しましょう。
ポイント2:省エネ基準を満たさない新築住宅は控除対象外
省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として住宅ローン控除を受けられません。これは、地球温暖化対策の一環として国が省エネ性能の高い住宅の普及を促進しているためです。
| 住宅ローン控除の借入限度額 | ||
| 2023年以前に入居 | 2024年以降に入居 | |
| 省エネ基準を満たさない 新築住宅・買取再販 |
3,000万円 | 0円※ |
※2023年までに建築確認を受けた新築住宅は2,000万円
-
【省エネ基準とは】
“省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなる。”
省エネ性能の高い住宅は光熱費が安く抑えられるため、資産価値も高くなる傾向です。これから新築住宅を建てる場合は、省エネ基準を満たす住宅かどうかも考慮しましょう。
ポイント3:子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置
住宅ローン控除には、子育て世帯や若者夫婦世帯(※)を対象とした優遇措置が設けられています。これは、子育て支援や若年層の住宅取得を後押しするための国の政策の一環です。
(※「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)
具体的な優遇措置の内容は次のとおりです。
| 新築・買取再販住宅 | 認定 | ZEH水準 | 省エネ | |
| 借入限度額 | 子育て世帯など | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| その他 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
参考:自民党「子育て世帯応援税制を延長 ここがポイント令和7年度税制改正大綱」
長期優良住宅やZEHなどの省エネ性能の高い住宅を取得する場合、より多くの控除を受けられます。ただし、今後の税制改正によっては優遇措置の内容が変更される可能性も否定できません。最新の情報を確認し、自分たちが優遇措置の対象となるかどうかを確認するようにしましょう。
ポイント4:新築住宅の床面積要件
住宅ローン控除を受けるには、「原則として、取得する住宅の床面積が50平方メートル以上」が必要です。
また、一定の要件を満たす場合には「床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満」の新築住宅であっても、住宅ローン控除の対象となる緩和措置が適用されます。
この緩和措置は、単身世帯や夫婦二人暮らしなど、コンパクトな住宅を求めるニーズに応えるためのものです。ただし、所得制限は合計所得金額1,000万円以下の世帯に限られるため、注意が必要です。
 住宅ローン控除でいくら戻ってくるかは、年収、住宅の種類(新築・中古、省エネ性能など)、住宅ローンの借入額、家族構成などによって異なります。ここでは、モデルケースを使って控除額のシミュレーション例を見ていきましょう。
住宅ローン控除でいくら戻ってくるかは、年収、住宅の種類(新築・中古、省エネ性能など)、住宅ローンの借入額、家族構成などによって異なります。ここでは、モデルケースを使って控除額のシミュレーション例を見ていきましょう。
住宅ローン控除額の計算式は次のとおりです。
-
【控除額】
住宅ローンの年末残高 × 控除率(原則0.7%)
【2024年に長期優良住宅に入居した子育て世帯の例】
- 2024年末時点での住宅ローン残高:4,000万円
- 所得税額:13万円
- 翌年の住民税額:24万円
この場合、まず住宅ローン控除額を計算します。
● 4,000万円 × 控除率(0.7%) = 年間最大控除額 28万円
次に、この控除額が所得税から引ききれるかを確認します。
● 所得税額13万円 - 控除額28万円 = -15万円
所得税額よりも控除額のほうが大きいため、所得税は0円です。次に住民税の控除を計算しますが、控除しきれなかった15万円がすべて適用されるわけではありません。翌年の住民税から差し引かれる上限は9.75万円です。
● 翌年の住民税額24万円 - 控除額9.75万円 = 実際に支払う翌年の住民税額14.25万円
結果として、このケースでは所得税13万円と住民税9.75万円、合計22.75万円の控除を受けることができました。
ただし、これはあくまで一例であり個々の状況によって控除額は異なります。金融機関や不動産情報サイトが提供しているシミュレーションツールを利用したり、専門家に相談したりして、自身のケースでの控除額を確認するようにしましょう。
 住宅ローン控除を受けるためには、所定の手続きを行う必要があります。初年度は確定申告、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きを行うのが一般的です。
住宅ローン控除を受けるためには、所定の手続きを行う必要があります。初年度は確定申告、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きを行うのが一般的です。
この章では、住宅ローン控除の申請方法と申請に必要な書類についてわかりやすく解説していきます。手続きの流れや必要書類を事前に確認して、スムーズに申請できるように準備しておきましょう。
初年度は確定申告が必要
住宅ローン控除を初めて受ける年(住宅に入居した年)は、会社員であっても原則として自分で確定申告を実施しなければなりません。
-
【確定申告とは】
“所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。”
引用:国税庁「確定申告とは」
確定申告をすることで、納め過ぎた所得税があれば還付を受けられます。確定申告書の作成方法については、国税庁のWebサイトで確認するか最寄りの税務署に相談しましょう。
必要書類と手続きの流れ
住宅ローン控除の申請には、確定申告書のほかにも登記事項証明書や売買契約書など、住宅の取得を証明する書類が必要です。
さらに、原則として2024年1月1日以降に入居する場合、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅であることを証明する書類を提出しなければなりません。具体的には、次のいずれかの書類を準備します。
- 建設住宅性能評価書の写し
- 住宅省エネルギー性能証明書
これらの書類は、通常、住宅の施工会社や販売会社から入手できます。住宅の引き渡し時などに受け取れることが多いので、確定申告に備えて早めに準備しておくと安心です。
住宅ローン控除は、必要書類が多く手続きが複雑に感じるかもしれません。しかし、税金の還付を受けられるメリットは非常に大きいです。初めての確定申告に不安な方は、税理士などの専門家に相談したり、税務署の相談窓口を利用したりすることをおすすめします。
2年目以降は年末調整でOK
住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の場合は、勤務先の年末調整で手続きが完結します。
-
【年末調整とは】
“年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。”
引用:国税庁「年末調整とは」
年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、下記の書類を勤務先に提出します。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
これらの書類は税務署や金融機関から送られてきます。この書類を年末調整で提出すると、勤務先の会社が住宅ローン控除額を計算し、所得税の還付や徴収を実施してくれるのです。
住宅ローン控除の申請期限を過ぎたらどうなる?
住宅ローン控除の申請期限(確定申告期限)を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。原則として、住宅に入居した年の翌年1月1日から5年間は「還付申告」をすることで住宅ローン控除を受けられます。
-
【還付申告とは】
“確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。”
ただし、期限を過ぎてからの申告となるため、還付金の受け取りが遅れたり、場合によっては加算税や延滞税が発生したりする可能性もあります。住宅ローン控除を受けるためには、できるだけ期限内に正しく申告するようにしましょう。

この記事では、住宅ローン控除の概要、控除額の計算方法、申請方法、必要書類などについて詳しく解説してきました。
住宅ローン控除を最大限活用するためには、最新の制度内容を理解し、自身がどの制度の対象となるか、いくら控除を受けられるかを把握しておくことが重要です。そして、事前に必要書類を揃え、期限内に正しく申請手続きを行いましょう。
住宅ローン控除は、マイホームの取得やリフォームを検討している方にとって大きなメリットをもたらす制度です。この記事で得た情報を参考に、住宅ローン控除を賢く活用して理想のマイホームを実現してください。
なお、UI銀行の住宅ローンは、お申し込みからご契約までの多くのお手続きをスマートフォンで対応できます。スマートフォン操作に不安がある方やじっくり相談したい方は、最寄りのきらぼし銀行窓口やローンプラザでも相談可能です。
「顔の見えるデジタルバンク」UI銀行の住宅ローンについて詳しく知りたい方は、ぜひ下記リンクをご覧ください。
\顔の見えるデジタルバンク!/
「UI銀行の住宅ローン」をチェックする
・住宅ローンを検討される場合には、別途当該商品の資料をよくお読みいただき、十分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断で行っていただくようお願いいたします。
・本記事は2025年3月30日の各種情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場や市場環境、制度の改正等を保証するものではありません。
企業プロフィール

株式会社UI銀行
UI銀行は、連携パートナーやきらぼし銀行を始めとしたきらぼしグループ各社と協働し、対面・非対面それぞれの良さを活かした多様なサービスを通じ、お客さまのお金だけでなく、健康や知識、人とのつながりといった見えない資産=「わたし資産」を増やすお手伝いをしていきます。

現在のあなたはどんなタイプ?9つのわたし資産の重要度をAIで判定!
あなた自身の多様な資産を知り、わたし資産をふやそう!
わたし資産スコアをためるとガチャ抽選で、プレゼントがもらえる企画を実施中!!